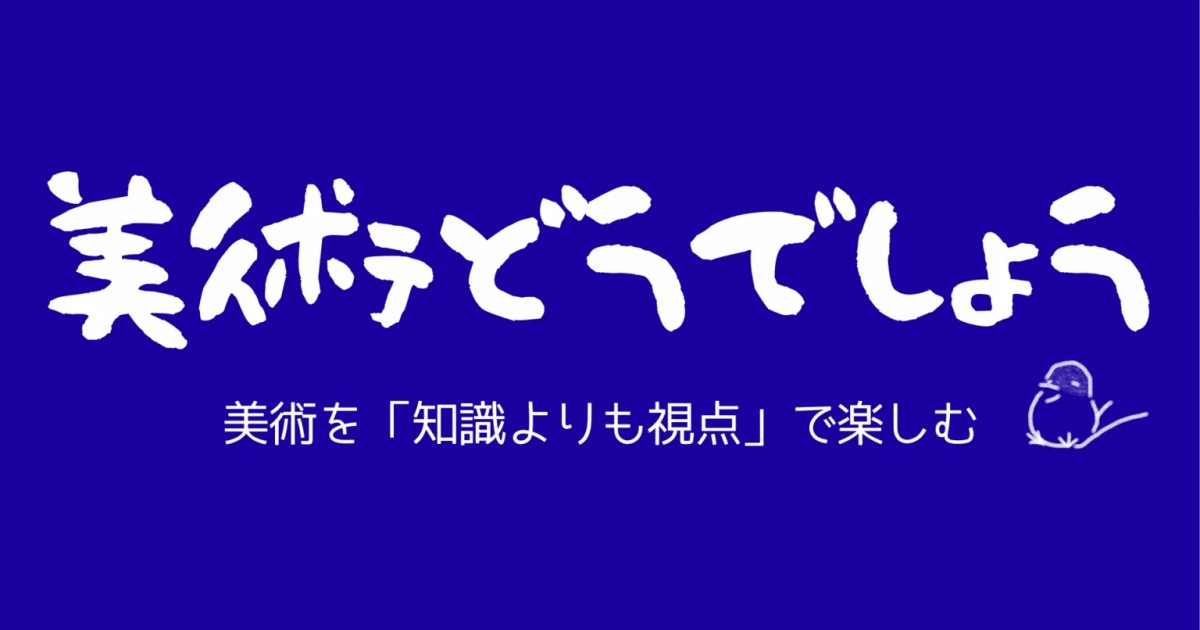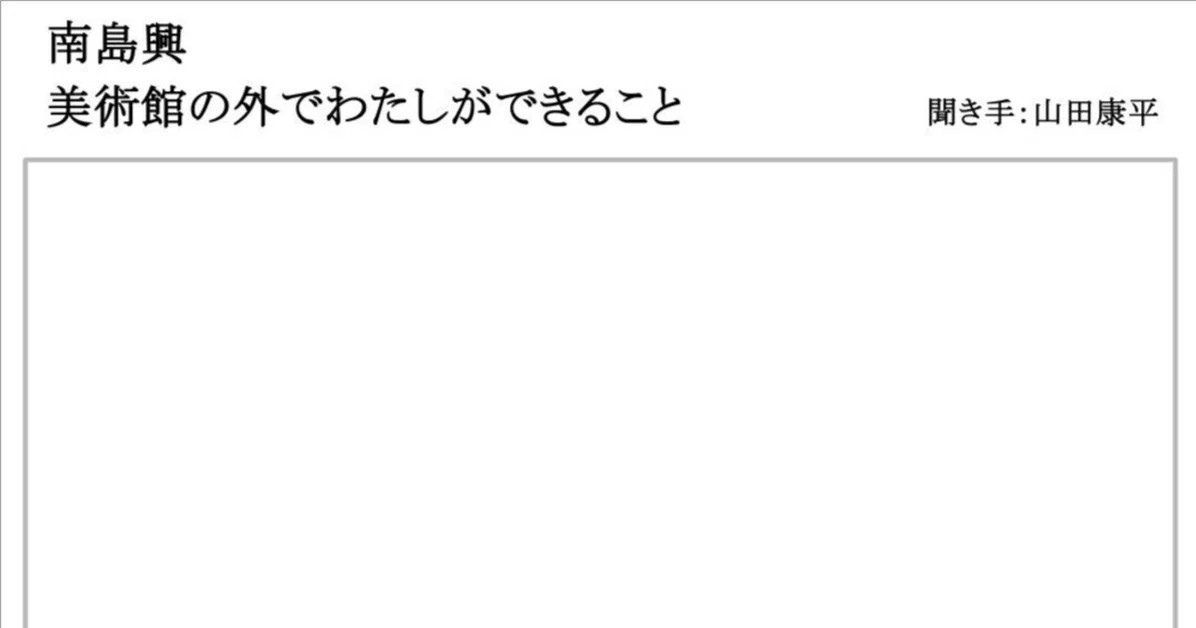現代書ってなんだ?
明日のトークぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
というわけで、明日に向けてプレゼン資料を冷や汗をかきながら、作成中の南島です。明日のアートジャーナリズムの夜は、はじめての試みで二部制に分かれています。前半がジャーナリズムパートで、上半期のアート界の主要トピックを3つ選んだので、それらについてひとりで話します。そして二部が、こちらに時間をしっかり取るつもりですが、現代書家の佐藤達也さんを特別ゲストに招いた「現代書の最前線」に迫るテーマトークのパートになります。一部はまだしも、二部に関しては1か月ほど前までは、かろうじて井上有一と篠田桃紅を知っているぐらいの書道/書の素人だったので、準備が追い付いているのが、いささか不安です。でも、井上らの1950-60年代の国際的な評価の微妙さと、その前史にあたる比田井南谷以降の書家たちの実験にこそありえたかもしれない現代書の可能性を感じたり、石川九楊の言う書の起源にある「筆蝕」は、ロザリンド・クラウス流のポストメディウム論に非常に相性がよいかもしれない、など自由連想的に面白い論点はいくつか見つかっています。時は1960年代から半世紀以上経ちましたが、改めて現代美術と現代書の間で生産的な議論ができたらと思っています。明日から、始まる気がしています。佐藤さんにはそういう熱気があります。

なんだ現代書かあ、佐藤さんってどなた?と思っている方にもぜひ見て欲しい企画です。これは美術、書に双方にとって、文字通りの意味で有意義なトークになること間違いなしです。